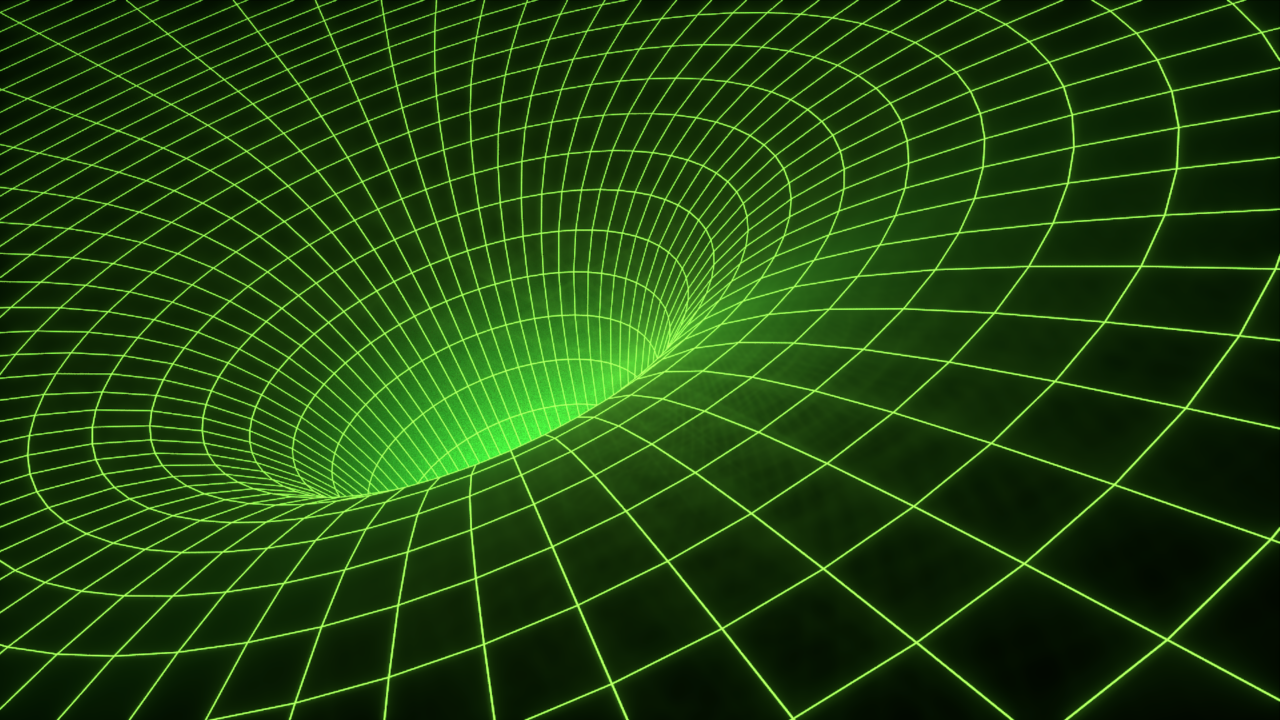Views: 96
ハンナ・アーレントの反ユダヤ主義の歴史的考察
ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』の第1巻では、ナチスの『反ユダヤ主義』はどのようにして形成されるに至ったかについての歴史的考察が述べられています。
どうしてユダヤ人はナチスによる大量虐殺の標的となったのか。
またユダヤ人を排斥するナチス党がなぜ民衆の熱狂的な支持を得るに至ったかについての考察です。
以下、ハンナ・アーレント 全体主義の起源 100分de名著(金澤大学法学類教授 仲正昌樹)を引用しています。

「全体主義の起源1-反ユダヤ主義」
かなり古くから、ユダヤ人に対する迫害は頻繁にありました。
社会不安や行き場のない怒りが鬱積(うっせき)すると、その矛先をユダヤ人に向け、集団的に迫害、追放、虐殺するポグロムと呼ばれる現象です。
しかし、19世紀の西欧社会に広がった反ユダヤ主義は、それとはまったく異なる政治的意味を持っているとアーレントは分析します。
反ユダヤ主義とユダヤ人憎悪は同じものではない。
ユダヤ人憎悪というものは昔からずっと存在したが、反ユダヤ主義はその政治的、及びイデオロギー的意味において19世紀の現象である。
ユダヤ人のなかには、すでにユダヤ人独特のライフスタイルを捨て、市民社会のなかに溶け込む人も増えていました。
ユダヤ教の信仰を捨てて、キリスト教徒になった人も少なくありません。
かなり社会に溶け込んでいたのに、19世紀になってユダヤ人は改めて迫害の標的とされてしまった。
それはその頃に西欧で勃興した近代的な『国民国家』が、憎悪の対象を必要としていたからであり、国家の求心力を高めるための『異分子排除のメカニズム』が働いていた、とアーレントは考察しています。
19世紀の反ユダヤ主義は、異教徒や異質な人間に対する漠然とした憎悪ではなく、国家の構造やイデオロギーと密接に結びついた現象だったというわけです。
国民国家の形成
19世紀ヨーロッパの歴史は、そのまま”国民国家形成の歴史”と言っても過言ではありません。
国民国家とは共通の社会・経済・政治生活を営み,共通の言語・文化・伝統をもつ,歴史的に形成された共同体を基礎として成立した国家を一般に指します。この意味で民族国家とほぼ同意に用いられます。
祖国たる土地を持たないユダヤ人は自分たちの国民国家を築ける状況ではありませんでした。
どこかの国に身を寄せざるを得なかったわけですが。どんなに地位があっても、異分子であることには変わりはありませんでした。
国民国家が形成されると、問題が起きます。
それは仲間と仲間ではない人の選別です。
当時、ドイツや東ヨーロッパ、ロシアには、かなりの数のユダヤ人が定住していました。
国家の中でそれなりに重要な役割を担っていた彼らをすべて追い出すわけにはいきません。
うまく『仲間』に取り込んでいくため、同化が進んでいたユダヤ人にも同権を保障する『ユダヤ人解放令』が各国で次々と出されました。
かつては『外』にあって憎悪の対象だったユダヤ人は、国民国家が形成される過程で『内』なる異分子となりました。
ここに『すでに奇妙な矛盾がひそんでいた』とアーレントが指摘しているのは、ユダヤ人を『内』に取り込むことが、実は先鋭的なユダヤ人排除の序曲となっていたということです。
ドイツがフランスという強い『敵』に遭遇することで覚醒した国民意識は、国民国家形成の原動力となりました。
しかし、フランスとの相違で育まれた仲間意識は、それを維持・強化するために、つねにあらたな『敵』を必要とします。
身近にいる誰かを、自分たちとは違うものとして仲間外れにしないと、自分たちのアイデンティティの輪郭を確認できないからです。
それまでバラバラだった国民が領土的、政治的に一つの形にまとまっていくと、より強力で安定した『仲間』関係を維持するため、まず他国民や他民族といった『異分子』を、できるだけ排除しようとします。
目に見える異分子を排除すると、次は自分たちの近くにいる『敵』を探し出し、それを排除することで同質性の純度を高め、求心力を保とうとする。
その標的となったのが、いったんは仲間として取り込んだ『ユダヤ人』でした。
ユダヤ人が標的となった原因は、他にもあります。
陰謀論の流布
ユダヤ人のなかには、国民国家が生まれる前の絶対的君主制時代、宮廷に仕えて国家の運営、特に経済官僚のような役目を担っていた人もいました。
19世紀に入ると培ったノウハウを活かして国際的な金融財閥を築く人たちが出てきます。
その好例がロスチャイルド家です。
ロスチャイルドは、もともとドイツを地盤として栄えた家系ですが、当主と5人の息子がそれぞれイギリスやフランスの君主に仕えることで、一族を国際的財閥に仕立て上げました。
彼らが圧倒的な存在感をもつようになると、あまり経済的に恵まれない非ユダヤ系ヨーロッパ人たちは、『ユダヤ人』が政治や経済を裏で動かしているのではないかと考えるようになります。
秘密結社のようなものが陰で社会を動かしているのではないかという幻想、まことしやかな陰謀説は昔からありました。
当時、ヨーロッパには千数百万人くらいのユダヤ人がいたはずですから、内実が見えにくいユダヤ人コミュニティを脅威に感じたとしても不思議ではありません。
ユダヤ人に対する疑いや妄想を膨らませる土壌となっていったわけです。
ユダヤ人が目立っていたのは、金融の世界ばかりではありません。
19世紀ドイツ語圏には東ヨーロッパから大量のユダヤ人が流入し、オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンでは大学教授の4割、医者や弁護士の5割前後がユダヤ人で占められるようになりました。
割合が増えると、実際の数よりも多く感じられるものです。
ドイツ系の一般市民や知的エリートにすれば、これも脅威であり、妬みや憎悪を増幅する一因となりました。
こうした状況はドイツ語圏のみならず、ヨーロッパ全体に広がっていました。
何かのきっかけでユダヤ人への憎悪が爆発してもおかしくない、そんな空気が漂っていました。
経済を牛耳っているのはユダヤ資本、アカデミズムで幅をきかせているのもユダヤ系の知的エリート。
そこに賄賂工作や機密情報の漏洩といった邪悪をイメージさせる事件が重なると、『シオンの賢者たちの議定書(※)』に書かれていたことが、現実味をもって民衆の間に浸透してしまう。
それが事実であるかどうかは、ここでは問題になりません。
(※)『シオンの賢者たちの議定書』は、「秘密権力の世界征服計画書」という触れ込みで広まった会話形式の文書。
1890年代の終わりから1900年代の初めにかけてロシア語版が出て以降、『シオンの議定書』『シオン長老の議定書』とも呼ばれる。
1921年にイギリスの「タイムズ」紙によって、偽書だったことが明らかになるが、すでにこれを読んでいた民衆はその計画を信じ、あからさまなユダヤ人排斥に拍車をかけることになった。
内容はユダヤ人が世界支配するという陰謀論であり、ヘンリー・フォードやヒトラーなど世界中の反ユダヤ主義者に影響を与えた。
結果的に国家社会主義ドイツ労働者党政権のドイツにおいてユダヤ人の大量虐殺(ホロコースト)を引き起こしたともいえることから「史上最悪の偽書」、「史上最低の偽造文書」ともとされる。
議定書の普及には、近代神智学の信奉者などオカルティストたちが積極的に動いた。
多くのオカルト結社やその周辺で、闇の勢力とは「ユダヤ」であると言われるようになり、ユダヤ陰謀論が盛んになった。
この文書はモーリス・ジョリー(フランス語版)著『マキャベリとモンテスキューの地獄での対話(フランス語版)』(仏語、1864年)との表現上の類似性が指摘されている。地獄対話はマキャベリの名を借りてナポレオン3世の非民主的政策と世界征服への欲望をあてこすったものである。
シオン賢者の議定書は地獄対話の内容のマキャベリ(ナポレオン3世)の部分をユダヤ人に置き換え、大量の加筆を行ったものとされる。
「シオンの賢者たちの議定書」を流布し、もともと存在した反ユダヤ主義をさらに強固なものとしたのは、他でもない大衆です。
オカルト結社や大衆が中心となり噂を広め、ユダヤ人に対する憎悪、反感が広がりました。
アーレントは「シオンの賢者の議定書」が流布する前から、ユダヤ人が秘密のユダ王国のようなものを作って世界征服を狙っているのではないかということを本気で心配している人々がおり、この偽書に飛びついたのだと指摘しています。
これを信じた民衆がユダヤ人への憎悪・反感を募らせていくと政治家は無視できなくなります。
そこにユダヤ人による不正(フランスのパナマ運河疑獄)が発覚すると、世の中は一気に反ユダヤ主義へと流れていきます。
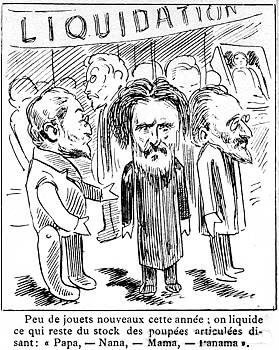
(パナマ事件の風刺画)
つまり、一言でまとめるならば、国民国家が形成される過程でユダヤ人の同化が進み、ユダヤ人が社会に溶けこんで活躍するようになればなるほど、ユダヤ人が国家を乗っ取り、世界征服をもくろんでいるように見え始めた、ということをアーレントは指摘しています。
国民意識を満足させる仮想敵はユダヤ人でなくとても、もしかすると誰でもよかったのかもしれません。
しかし、古くからヨーロッパ各国における迫害の対象であり、しかも国民国家の内部に入り込んで見えにくくなっていたユダヤ人は、国を内側から侵食する『敵』としてイメージされやすかったのです。
『社会の敵』としてのユダヤ人のイメージが西欧諸国で広まると、民衆の感情を利用した反ユダヤ主義政党も現れます。
アーレントはこうした動きに着目し、全体主義、ひいてはナチスによるユダヤ人問題の『最終解決』へとつながる起源としたのです。